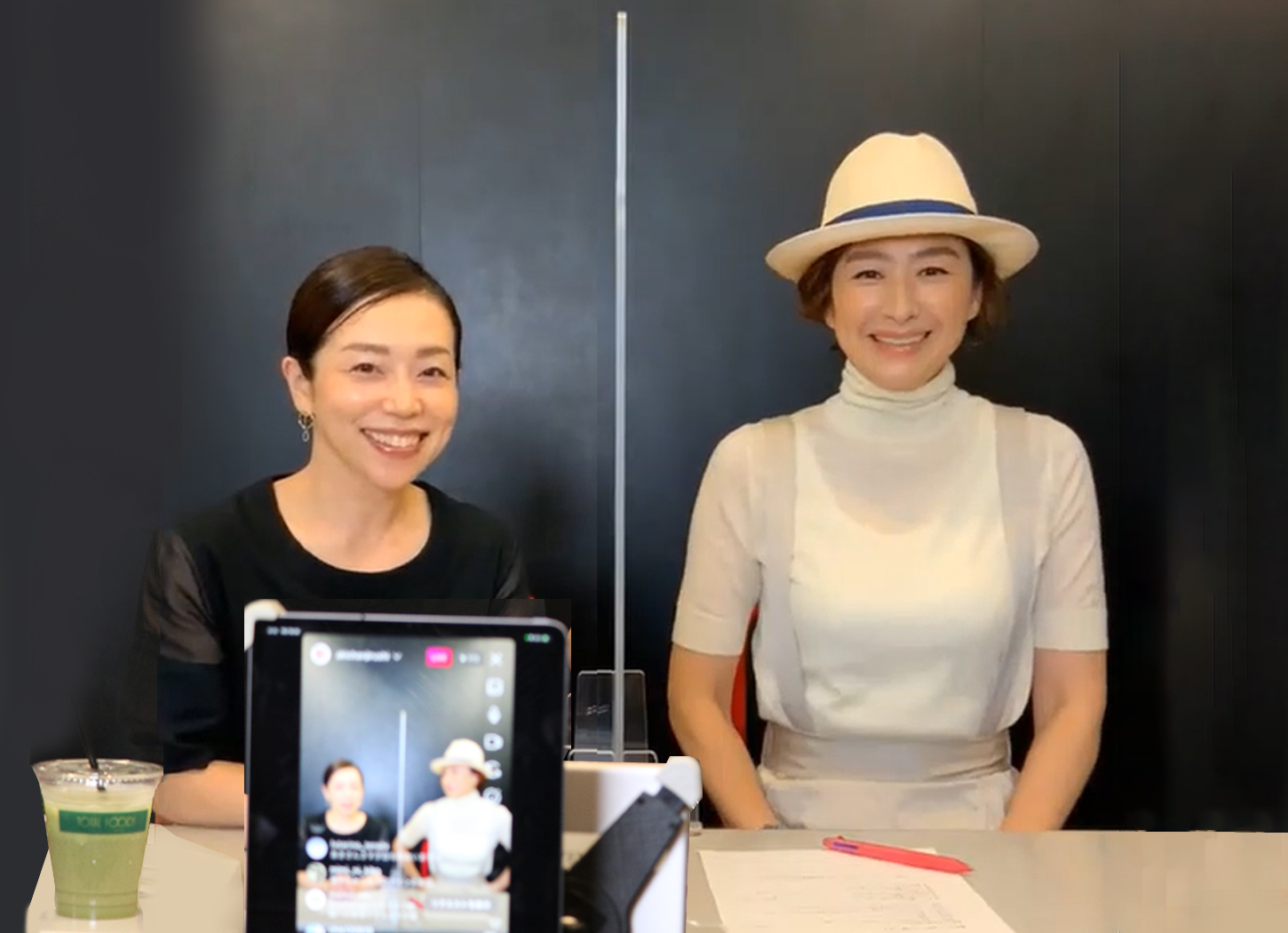筋トレをする人にとって筋肉の材料になるタンパク質の摂取は必要不可欠!
とはいえ、タンパク質を摂取する量やタイミング、頻度についてしっかり把握できていない、という人も多いはず。
タンパク質にも効果的な摂取方法があります!
この記事では栄養学とカラダをかえるプロであるパーソナル・トレーナー、およびエビデンスに基づき、筋トレ中の食事制限とタンパク質の効果的な摂取方法について解説します。
ぜひ最後まで読んで効果的なタンパク質の摂取方法を学び、あなたの筋トレの効果を高めてください。
タンパク質は「一番大切なもの」

タンパク質は英語でProtein(プロテイン)。
語源はギリシャ語で、その意味は「もっとも大切なもの」。タンパク質は筋肉、肌、皮膚、髪、内臓など、カラダのさまざまなパーツの材料になります。筋トレだけではなく、人間のカラダに不可欠な栄養素です。
そしてタンパク質は数十個のアミノ酸がつながって構成されています。摂取したタンパク質は、小腸でアミノ酸に分解されて体内に吸収されるため、体内ではアミノ酸として働きます。
必須アミノ酸は食事から摂取すべき
アミノ酸は20種類あり、9種類の必須アミノ酸と11種類の非必須アミノ酸に分けられます。
| 必須アミノ酸9種類 | バリン・ロイシン・イソロイシン・リジン・メチオニン・フェニルアラニン・スレオニン・トリプトファン・ヒスチジン |
|---|---|
| 非必須アミノ酸11種類 | グルタミン・アルギニン・システイン・アスパラギン・グリシン・アラニン・プロリン・チロシン・セリン・グルタミン酸・アスパラギン酸 |
必須アミノ酸は体内で合成できないため、食事やサプリメントから摂取しなければなりません。一方で非必須アミノ酸は体内で合成できるため、必ずしも食事からの摂取が必須ではありません。
なぜアミノ酸の解説をしたかというと、タンパク質は「質」が重要だからです。タンパク質の「質」は「アミノ酸スコア」という指標によって表されます。
アミノ酸スコアが高いタンパク質を選ぶ!
アミノ酸スコアは食品のタンパク質の栄養価を表す指標で、必須アミノ酸がバランス良く含まれているかを数字で表しています。
先ほど解説したように、タンパク質は小腸でアミノ酸に分解されて体内に吸収されます。そのため「どのアミノ酸でそのタンパク質が構成されているか」がとても重要です。
タンパク質量が多くても必須アミノ酸の種類が少なければ、アミノ酸スコアが低い=タンパク質の質が低い、ということになります。
先ほど解説したように、必須アミノ酸は食事からの摂取が必須です。アミノ酸スコアが低い食品を大量にとってタンパク質の量を満たしても、必須アミノ酸が不足してしまう可能性があります。
アミノ酸スコアは肉類や魚介類、卵や乳製品などの動物性食品が高い傾向にあり、植物性食品が低い傾向にあります。筋肥大が目的の場合も健康維持が目的の場合も、アミノ酸スコアの高いタンパク質の摂取が重要です。
いつ摂ればいい?筋トレに効果的なタンパク質を摂るタイミング

筋肥大させるために有効なタンパク質の摂取タイミングは、明確にはわかっていません。*3
しかし筋肉は、血中アミノ酸濃度が高いと合成が活発になり、低いと分解が活発になると考えられています。そのため、血中アミノ酸濃度を特に高めたい以下の3つのタイミングでタンパク質を摂取しましょう。
- トレーニング前後
- 就寝前
- 朝食前
筋トレ前後のタンパク質摂取
筋トレ開始直後から筋肉の合成と分解が活発化するため、筋トレ前後のタイミングでタンパク質を摂取して、血中アミノ酸濃度を高めることが重要と考えられています。
血中アミノ酸濃度がピークを迎えるまでの時間は、一般的な食事か、サプリメントかによって以下のように違います。
- 一般的な食事:2時間
- プロテイン:1時間
- アミノ酸(BCAA・EAAなど):30分
食事は筋トレ2時間前に終わらせましょう。プロテインなら1時間前、BCAAやEAAなどのアミノ酸は30分前に飲むといいです。筋トレ中は消化吸収のエネルギー消費が少ないアミノ酸がおすすめです。
あまりにも空腹の状態で筋トレをすると、トレーニングのエネルギーを作り出すために筋肉を分解してしまうことがあるのえ注意しましょう。
そして、筋トレ終了直後も筋肉の合成が高まっていると考えられているため、運動後すぐにタンパク質を摂取しましょう。このときは吸収率の高いホエイプロテインやその他のプロテイン、高タンパク質の食事がおすすめです。
筋トレと食事の関係については以下の記事でも詳しく説明していますので、参考にしてみてください。
就寝前
就寝中にカラダが回復するとき、より筋肉の合成が期待できるため、就寝前にタンパク質を摂取して血中アミノ酸濃度を高めましょう。*4
また、就寝後は数時間にわたってタンパク質補給ができません。そのため深夜から早朝にかけてはどうしても血中アミノ酸濃度が低下してしまいます。血中アミノ酸濃度が低下する時間を最小限にするためにも、就寝前のタンパク質摂取がおすすめです。
しかし、就寝直前に消化の負担が大きい肉類や乳製品を食べてしまうと、寝ている間に消化にエネルギーを使い、睡眠が浅くなってしまう可能性があります。そのため、就寝前はプロテインがおすすめです。
朝食時
起床時は、前夜のタンパク質摂取から数時間が経過しているため、血中アミノ酸濃度が低下した状態です。筋肉が分解されやすい状態なので、素早くタンパク質を摂取して血中アミノ酸濃度を高めましょう。
おすすめは素早く消化吸収されるBCAAやEAAなどのアミノ酸のサプリメントです。起床後すぐにアミノ酸のサプリメントを飲んで、その後素早く高タンパク質の食事を摂りましょう。
たんぱく質摂取量目安

カラダの中のタンパク質は分解と合成をくりかえし成人の場合一日に約200~300gのタンパク質が体内で分解され、再合成しきれない25%(約70g前後)を食事から摂る必要があります。
タンパク質70gの具体的な例は
卵 11個
豆腐 3丁
鶏胸肉 1.5枚
です。なかなかの量だと思いませんか?
筋トレをしない方のタンパク質摂取量目安
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」で推奨されているタンパク質の摂取量は以下のとおりです。*2
- 男性(18〜64歳)65g/日
- 女性(18〜64歳)50g/日
こちらは健康維持するための必要最低限の摂取量です。筋肥大やダイエットのために筋トレをする人は、もっと必要量が増えます。
筋トレをする方のタンパク質摂取量目安
筋トレによって十分な負荷を筋肉に与えると、筋繊維は微細に損傷します。その後およそ48〜72時間かけて、微細に損傷した筋繊維が以前よりも太くなりながら回復します。 これを超回復といい、筋トレによって筋肉が成長するメカニズムの1つです。
そして超回復のためには、筋肉の材料となるたんぱく質が必要です。そのため筋トレ中は、必要なタンパク質量も増えるため、食事やサプリメントからより多くのたんぱく質を摂取しなければなりません。
筋トレをしている人は、体重1kgあたり1日1.5〜2.5gが摂取量の目安です。体重60kgの人なら90gから150gを1日に摂取しましょう。
主要な食品のタンパク質含有量と摂取量の目安

続いて、一般的なスーパーで購入できるタンパク質の含有量が多い食材を紹介し、推奨摂取量を解説します。推奨摂取量は筋トレをしない人・する人で変わります。
主要な食品のタンパク質含有量
最初に、文部科学省の食品成分データベースから、スーパーで購入できる食材でタンパク質の含有量が多い食材を紹介します。*1 すべて可食部100gあたりのタンパク質含有量です。
肉類
以下はすべて、焼いた場合のタンパク質含有量です。脂質の少ない肉ほど、タンパク質が多い傾向にあります。
- 豚ヒレ:39.3g
- 鶏むね(皮付き):34.7g
- 鶏ささみ:31.7g
- 牛もも:28g
- 牛ヒレ:27.2g
牛のホルモンなどはとろけるようなくちどけ通り脂肪分がかなり多いので筋トレ時には向きません。
ハムやベーコンといった加工肉は添加物が気になるところ。原材料を確認し便利さと健康を天秤にかけて賢くチョイスしましょう。
魚介類
以下はすべて、焼いた場合のタンパク質含有量です。
- しろさけ:29.1g
- くろまぐろ(養殖):29g
- まるあじ:28.7g
- べにざけ:28.5g
- まこがれい:28.5g
カツオは糖質の代謝に重要なビタミンB1が多く筋トレに適したタンパク質と言われています。とはいえ秋の戻りガツオはかなり油がのっているのであまりお勧めできません。カツオは春獲りの方が筋トレに向いています。
かまぼこやちくわなど、魚介の練り物は手軽に食べられるという利点がありますが、糖質が高めで、添加物の有無も気になるところです。
乳製品(チーズ)
乳製品の中でも、チーズはタンパク質が豊富です。ただし、脂質も高いです。
- パルメザンチーズ:44g
- チェダーチーズ:25.7g
- プロセスチーズ:22.7g
- カマンベールチーズ:19.1g
- モッツァレラチーズ:18.4g
- カッテージチーズ:13.3g
ヨーグルトを食べる場合は低脂肪で糖質が添加されていないものを選びましょう。
手軽にできる高タンパク質レシピ

鶏胸肉の塩麹焼き
腸内細菌がよろこぶ発酵食品塩こうじも摂れるレシピです。
冷めても柔らかいのでお弁当にもおすすめ。
- 鶏胸肉1枚の皮を取り除き、薄めのそぎ切りにする。
- 塩麴大さじ2を塗り冷蔵庫で一晩ほど漬け込む。(時間がない時は最低30分)
- ごま油少量を入れたフライパンで両面焼く。
塩麴が焦げやすいので、軽く拭きとってからソテーするとよい。
お豆腐を塩麴に漬けておくのもお勧めです。
無脂肪豚とキノコのソテー
代謝に欠かせないビタミンB1を摂れる豚肉の料理です
- 豚もも肉の赤身部分をスライスし沸騰した湯にくぐらせ油を落とし冷水で洗う。
- 生姜だれをつくる。
小鍋に おろししょうが10g ダイエットめんつゆ20cc 水10cc ラカンカ甘味料もしくはてんさい糖少々 少々を入れひと煮たちさせる。水溶き片栗粉少々を加えてとろみをつける。
- テフロン加工のフライパンで しめじ20g えのき10g 玉ねぎスライス20g をソテーし、1と2を加え絡める。
カツオの柚子胡椒焼き
カツオはお刺身でもOKですが、生臭さが気になる人は柚子胡椒でマリネしてから焼くことで美味しく食べられます。
- カツオの切り身(30gx3切れ程度)に塩を振ってしばらく置く。
- マリネ液を作る。
- 柚子胡椒5g ダイエットめんつゆ20g ラカンカ甘味料かてんさい糖10g を混ぜ合わせる。
- マリネ液にカツオと、斜め切りにした長ネギを入れ2時間ほど冷蔵庫でマリネする。
- テフロン加工のフライパンで焼く。
<ダイエットめんつゆ>
しょうゆ100cc 日本酒100cc 水200cc ラカンカ甘味料またはてんさい糖少々 和風だし少々 だし昆布半分
全てを鍋に入れひと煮たちさせ冷蔵庫で保存。
ツナ缶のチャプチェ風
ツナ缶は必ずノンオイルのものを使い、煮汁は軽く絞ってから使います。
きくらげ以外に、キノコ類を使用することで食物繊維も摂ることができます。
- 白滝を食べやすい長さにカットし熱湯にくぐらせる
- きくらげを水で戻し食べやすいサイズにカット
- テフロン加工のフライパンで油を使用せず白菜、ツナ、白滝、きくらげを炒め、ダイエットめんつゆで味付けする。
オクラ入りいか納豆
腸が喜ぶ発酵食品納豆と、ネバネバ食物繊維のオクラで便秘解消も期待できます。
- オクラ4本をさっとゆでて小口切りにする
- ボウルに納豆1パックをいれ、オクラ、刺身用イカ(細切り)、醤油小さじ1を加えて混ぜる。
自家製サラダチキン
筋トレ中のタンパク質摂取の強い味方サラダチキン。コンビニなどでも買うことが出来ますが自家製だと無添加で安心安全なのが嬉しいもの。
鶏胸肉を皮ごと調理し「皮は食べない」がしっとりおいしいサラダチキンをつくるポイントです。
- 胸肉1枚に塩、ラカンカ甘味料もしくは甜菜糖少々をふり2時間ほど冷蔵庫で寝かせる。
- 水けをペーパーでふき取り好みのマリネ液で1日ほどマリネする。
- 蒸し器で蒸すか、テフロン加工のフライパンでソテーする。
マリネ液
日本酒 10cc
しょうゆ 3cc
ラカンカ甘味料もしくは甜菜糖 4g
+
豆板醤6g or ゆずこしょう4g or わさび4g などお好みの香辛料
醤油の代わりに塩2gにし、バジルなどのドライハーブを入れるのもおすすめです
市販のサラダチキンの選び方や、その他の肉料理については以下の記事も参考にしてみて下さい。
プロテインでタンパク質を摂取する場合のポイント

一度に大量より小分けに摂取
一度の食事で吸収できるタンパク質量は30gという説がありますが、根拠はありません。そのため一度の食事で吸収できるタンパク質量の明確な数値は現状ありませんが、体重1kgあたり0.25g、もしくは20〜40gほどのタンパク質量が最適と考えられています。*5
そのため、一度に大量のタンパク質を摂るよりも分割して摂取しましょう。分割することで、血中アミノ酸濃度が高い状態を維持できます。
実際に、タンパク質を摂取する回数を1日6回に増やすことで、除脂肪体重が増えて脂肪が減少したと報告されています。*6
通常の3食に加えて、2回の間食と就寝前にプロテインを活用すれば、1日に6回タンパク質を摂取できます。
プロテインの種類
効率という点ではアミノ酸スコアの高いホエイプロテインが筋トレにはお勧めですが、体質や用途により使い分けましょう。
乳由来のホエイプロテイン
プロテインを飲むとお腹がぐるぐる鳴る、おならがよく出るなどの体験談が多いことから、プロテインで腸内環境が悪化するという説もありますがホエイプロテインの中でも乳糖が含まれるWPC(ホエイプロテインコンセントレート)だとお腹の調子が悪くなる人がいます。その場合はWPI(ホエイプロテインアイソレート)
を試すことでお腹の不具合が解消される可能性があります。
WPCよりWPIは少し割高ですが、その分タンパク質の含有量が多く吸収率も高いため、タンパク質量あたりの金額で比較すると大差はありません。
植物性プロテイン~ソイ(大豆)
植物性プロテインの中でも味が良いため好まれます。
女性ホルモンにも関与するところが利点でもありますが、女性特有の病気に罹患した経験のある人は医師に確認をする必要があります。大豆アレルギーのある人も飲むことが出来ません。
植物性プロテイン~えんどう豆
水溶性食物繊維が豊富で腸内環境にもうれしいピープロテインはSDGsの観点からも注目度の高い植物性プロテインです。アレルギー食品に該当しないため安心感が高く、また、筋合成に重要なBCAA(バリン・ロイシン・イソロイシン)を豊富に含んでいるため植物性プロテインの中では筋トレ効率アップに適していると言えるでしょう。
ソイ、ピー(えんどう豆)ともにホエイと比べると消化吸収の負担が軽いので、寝る前の空腹対策や回復力アップを目的にプロテイン摂取する際のチョイスとしておすすめです。
プロテインの選び方については、以下の記事も参考にしてみてください。
筋トレとタンパク質に関するよくある質問

最後に、筋トレとタンパク質に関するよくある質問にお答えします。
- タンパク質を摂りすぎるとどうなる?
- 筋トレをしない日も摂ったほうが良い?
- 筋トレ中はやはりお酒は飲まない方がいいの?
Q:タンパク質を摂りすぎるとどうなる?
タンパク質を摂りすぎると太る?
理論上は余分なタンパク質は脂肪になる可能性がありますが、体重1kgあたり1日4.4gのタンパク質摂取を8週間続けた実験では、体脂肪は増加しなかったと報告されています。*
一方でこの実験では除脂肪体重も増えなかったため、推奨される体重1kgあたり1日1.5〜2.5g以上のタンパク質摂取をしてもあまり意味がないようです。
タンパク質の「質」には注意しましょう。脂質の多いタンパク質や、調理方法によってはカロリー過多になり太る可能性があります。
Q:タンパク質を摂りすぎると腎臓に負荷がかかる?
タンパク質を摂りすぎると処理する腎臓に負荷がかかりすぎるという説がありますが、現状はタンパク質を摂りすぎることの悪影響に明確な根拠はありません。厚生労働省もタンパク質の摂取量は腎機能との関連が深いとしているものの、耐容上限量は設定していません。*7
ただし、タンパク質を多く摂取することで、カロリーオーバー、脂質が高くなりすぎるデメリットもあります。摂取すべきカロリーを目安に、摂りすぎには注意しましょう。
短期間で効率的にカラダを変える為に高タンパク質に偏った食事をする際は、3週間程度を目安に、期限をもうけることをおすすめします。
Q:筋トレしない日もタンパク質を摂ったほうが良い?
筋トレ後は、48時間以上筋タンパク質の合成が高い状態が続きます。*8 そのため筋トレをしない日もタンパク質を摂取しましょう。
先ほど解説したとおり、血中アミノ酸濃度が高いと筋肉が合成されやすくなり、低いと分解されやすくなります。そのため筋トレをしばらくしなかったとしても、筋肉量を維持するため、日常生活で消費されるタンパク質を補うためにはタンパク質の豊富な食事を摂り続けることをおすすめします。
Q:筋トレ中のお酒はNG?
筋トレの後にお酒を飲むと、肝臓におけるアルコール分解にエネルギーが使われてしまい、筋肉にまわすエネルギーが不足してしまいます。
せっかく筋トレをして、しっかりタンパク質を摂っても、筋肥大、それにともなう代謝のアップにつながりづらくなってしまうのでお勧めできません。
どうしてもお酒を飲む場合は「筋トレをしない日」「お酒のチョイスや回復力を高める工夫をする」ことを忘れずにやりましょう。
詳細は以下の記事を参照してください。
タンパク質を効果的に摂取して筋トレの効果を高めよう

筋トレ中は、1回20〜40gほどのタンパク質を1日5~6回に分けて摂取するのがおすすめです。1日の合計摂取量の目安は、体重1kgあたり1.5〜2.5g。体重60kgの人なら、90〜150gです。1回20gのタンパク質を1日6回に分けて摂れば20g×6回=120gとなります。
タンパク質を摂りすぎると健康に悪影響という説もありますが、現状は明確な根拠がなく、厚生労働省も耐容上限量は設定していません。
とはいえ、人間のカラダは環境に順応すると変化が出づらくなるので、短期間でカラダをかえるための高タンパク質食を行う場合は、3週間を目安に、一定の期間を設けることをおすすめします。
そして、筋タンパク質の合成はタンパク質だけではできません。筋トレ中に糖質をエネルギーにするためにも、脂肪を分解するためにも、代謝を助けるビタミンなどの補酵素が必要です。筋トレ中は特に、ビタミンC、B1、B2、B6、Dもしっかり摂りましょう。
筋トレ中の食事に関しては、以下の記事もぜひ参考にしてください。
もし自分で実践するのが難しい場合はパーソナル・トレーニングがおすすめです。プロのトレーナーから、あなたにパーソナライズされた食事指導を受けられます。
効率よくタンパク質を摂って、あなたの筋トレの効率を高めてください。
- タンパク質とアミノ酸 前編 ー 山本義徳業績集2
- ビタミンのすべて ー 山本義徳業績集6
- *1 食品成分データベース ー 文部科学省
- *2 日本人の食事摂取基準(2020 年版) ー 厚生労働省
- *3 The effect of protein timing on muscle strength and hypertrophy: a meta-analysis ー J Int Soc Sports Nutr. 2013 Dec 3;10(1):53. doi: 10.1186/1550-2783-10-53.
- *4 Pre-Sleep Protein Ingestion to Improve the Skeletal Muscle Adaptive Response to Exercise Training ー Nutrients. 2016 Nov 28;8(12):763. doi: 10.3390/nu8120763.
- *5 International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise ー J Int Soc Sports Nutr. 2017 Jun 20;14:20. doi: 10.1186/s12970-017-0177-8. eCollection 2017.
- *6 Increased protein intake and meal frequency reduces abdominal fat during energy balance and energy deficit ー Obesity (Silver Spring). 2013 Jul;21(7):1357-66. doi: 10.1002/oby.20296. Epub 2013 May 23.
- *7 The effects of consuming a high protein diet (4.4 g/kg/d) on body composition in resistance-trained individuals ー J Int Soc Sports Nutr. 2014 May 12;11:19. doi: 10.1186/1550-2783-11-19. eCollection 2014.
- *8 Mixed muscle protein synthesis and breakdown after resistance exercise in humans ー Am J Physiol. 1997 Jul;273(1 Pt 1):E99-107. doi: 10.1152/ajpendo.1997.273.1.E99.
- *9 Ingestion of whey hydrolysate, casein, or soy protein isolate: effects on mixed muscle protein synthesis at rest and following resistance exercise in young men ー J Appl Physiol (1985). 2009 Sep;107(3):987-92. doi: 10.1152/japplphysiol.00076.2009. Epub 2009 Jul 9.