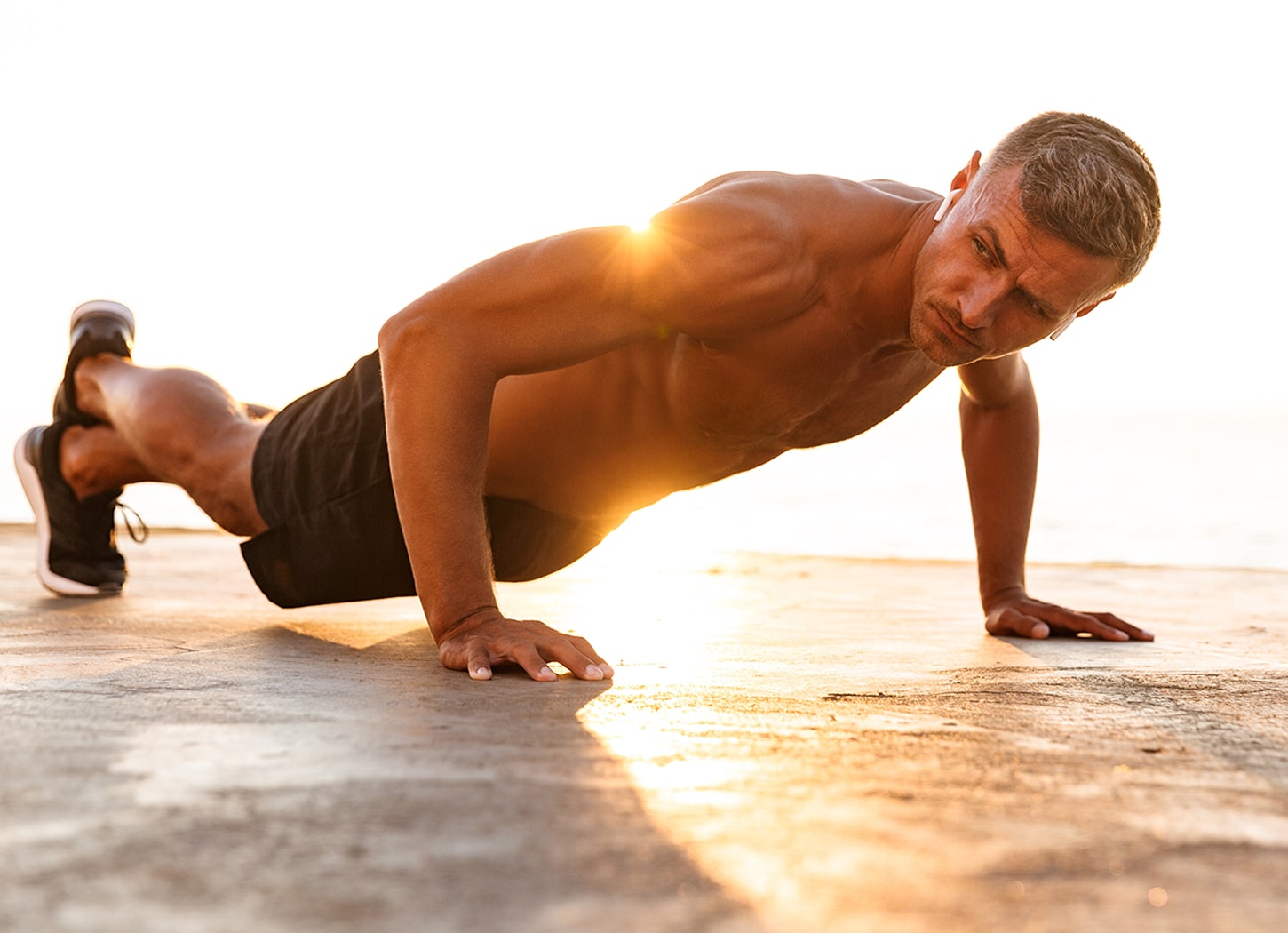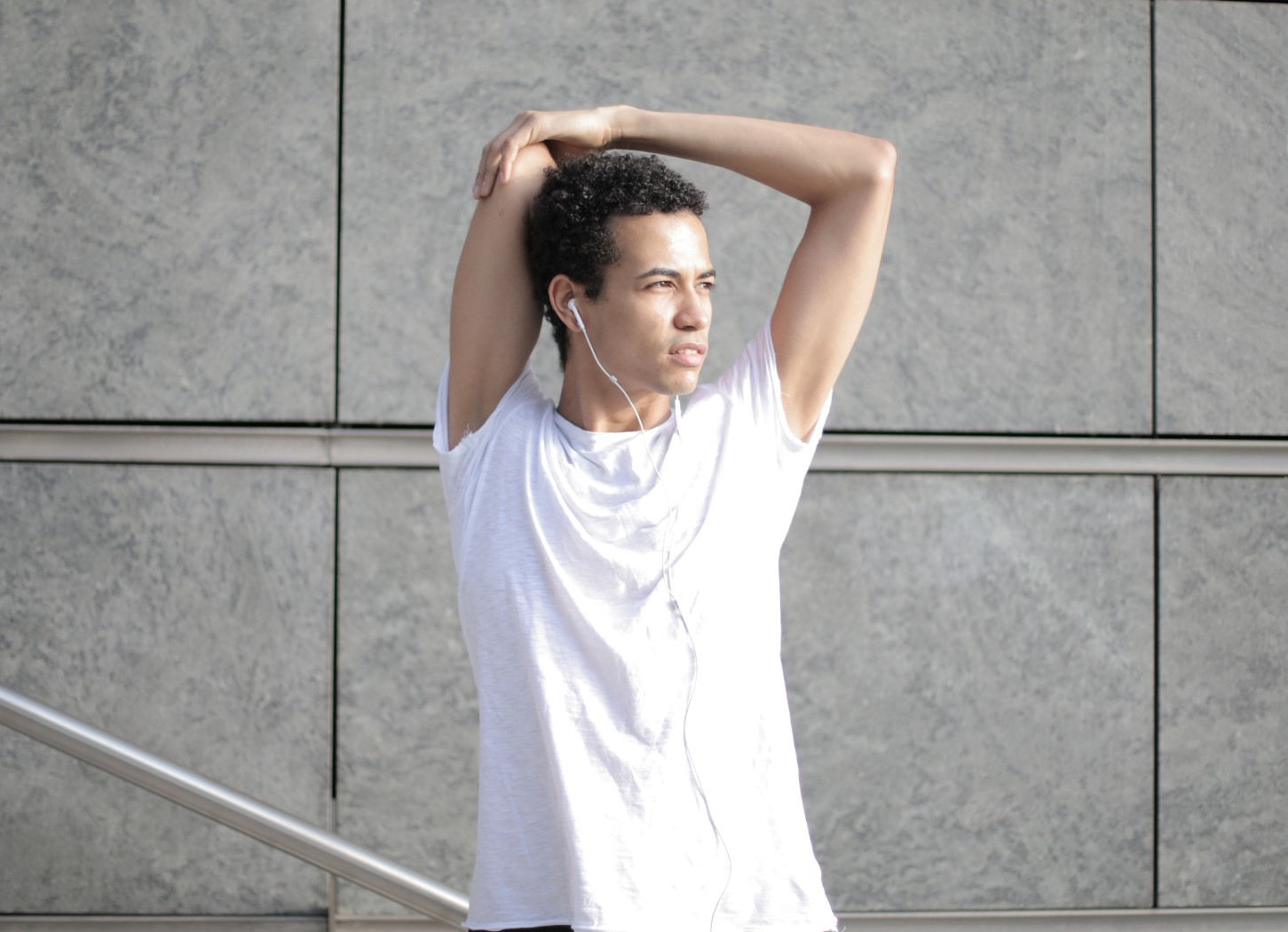筋トレは毎日した方がいいのか?それとも毎日は逆効果なのか?疑問を抱いて、頑張り切れない方も多いのではないでしょうか?
2023年秋、厚生労働省が健康づくりのために推奨する身体活動・運動の目安となるガイド案を10年ぶりに改訂し、筋力トレーニングは、成人・高齢者ともに週2~3回を推奨したことは、大きく話題に取り上げられました。
この記事では効率的な筋トレの頻度や、なぜ週2~3回が推奨されるのか?そして毎日筋トレする場合の注意点と、トレーニングの具体的なメニューについてパーソナル・トレーナー監修のもと解説します。
自分に合った筋トレプランを組んで、なりたいカラダやライフスタイルを手に入れる効率をアップしてください。
筋トレの最適頻度は週2~3回

WHOが示している「身体活動・座位行動ガイドライン」(*1)にて、成人では健康増進のために週に2日以上、全ての主要筋群を使用して実施する中強度以上の強度の筋力行動活動を行うことが推奨されています。
パーソナル・トレーニングジム「トータル・ワークアウト」でもまた、多くのメンバーに対して週2~3回の筋トレでの効率的なカラダづくりを実施しています。その理由を以下で解説します。
筋肉の成長には回復が必要だから
筋トレで傷ついた筋肉は、48時間~72時間かけて回復しながら成長します。
回復の期間が足りなかったり、期間が空きすぎてしまうと効率的な成長が見込めません。
そのため、同じ部位は2〜3日空けてから鍛える必要があるのです。
たとえば、月曜日に上半身を鍛えたら、次に上半身を鍛えるのは木曜日以降です。逆に間を空けすぎるとまた筋肉が元に戻ってしまうので、回復したらできるだけ早くその部位の筋トレをしましょう。
そのため、同じ部位の筋トレは週2〜3回が理想です。
部位を細分化すれば毎日の筋トレでも問題ないですが、生活スタイルを考慮すると週2~3回が現実的と言えるでしょう。
習慣化しやすい現実的な頻度だから
毎日筋トレをしても逆効果にならない方法もあります。
ただし、忙しい現代人にとって毎日筋トレをする時間を設けるのはかなり難しいのが事実。
現実的に時間を取れるのが週2~3回。
実現可能な頻度が、筋トレの習慣化と継続のカギになります。
毎日筋トレをするデメリット
デメリット❶ 超回復の期間がとれない・オーバーワークになる
デメリット❷ 怪我・筋肉痛のリスク
デメリット❸ 疲労蓄積による効率ダウン
デメリット❹ 時間の確保ができず挫折する
デメリット❶ 超回復できない・オーバーワークに陥る
回復が不十分な状態で筋トレを行うと、疲労>回復のオーバーワーク状態になり筋肉が効率的に成長しません。
辛い筋トレをしても効果が出ないのは、精神的にも辛いものです。
デメリット❷ 怪我・筋肉痛のリスク
ベストコンディションでないのに最大の負荷でトレーニングをしてしまうと、オーバーワークどころか怪我をする場合があります。怪我をしてしばらく筋トレができないと、筋肉の成長に支障をきたし非効率的であることは言うまでもありません。
デメリット❸ 疲労蓄積による効率ダウン
疲労がたまり、通常であれば挙げられる負荷や回数をこなせないなど、トレーニング自体の強度が下がると効果が出づらくなってしまいます。
また、仕事や日常生活でこなすべき物事の効率までダウンしてしまうリスクがあります。
デメリット❹ 時間の確保ができず挫折する
毎日筋トレの時間を確保するのは物理的にも精神的にも大変です。
大きな目標たて、それを実現できないからと全てをあきらめてしまうよりは、小さな目標を1つ1つこなすほうが成功可能性が高くなります。なので、実現可能な筋トレ頻度を見極めることが重要なのです。
これらのデメリットを踏まえた上で、対策やケアをしないと毎日の頑張りが無駄になることがあります。
毎日筋トレをするメリット、デメリットについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
毎日筋トレする場合におさえるべきポイント

筋トレを毎日行う際のデメリットを考慮しつつ、日々違う部位を鍛えるのであれば、筋トレは毎日やっていいです。
逆に、筋トレを週1回しかできないのは良くない、意味がいない、というのも間違い。
週2~3回以外の頻度で筋トレをする際のポイントについて解説します。
毎日筋トレのポイント❶ 筋トレ部位を細分化する
ボディビルダーのような筋トレ上級者の中には、日ごとに腹・胸・背中・肩と腕・脚など、カラダを5分割にし、1日1部位・週4日~毎日ピンポイントで徹底的に追い込むという人も多いです。
部位を細分化することで、時間をかけてじっくりと追い込むことができます。
毎日筋トレのポイント❷ 毎日やってもOKな筋トレ
大きな筋肉をつけるのではなく、健康維持や体力向上、ゆるやかなダイエットを目的にする人は、筋肉痛にならない程度の軽い負荷の筋トレであれば毎日やっても問題ないです。
また、腹筋や二の腕といった小さな筋肉ほど回復が早いので、体幹を鍛えるような自重筋トレであれば毎日行ってもオーバーワークになるリスクは低いでしょう。
毎日筋トレのポイント❸ ストレッチや有酸素運動は毎日やってもいい
ウォーキングなどの軽い有酸素運動や、10分程度のストレッチであれば、むしろ毎日やった方がいいでしょう。
ダイエットが目的でトレーニングを検討している人は、ランニングなどの有酸素運動に着手する人が多いですが、ダイエットや引き締めには大きな筋肉を鍛えてカラダの基礎代謝を上げること、つまり無酸素運動(筋トレ)のほうが効率がよいです。
筋トレのための体力を構築する、筋トレしない日のアクティブレストに有酸素を組み込む、ランニングでストレス発散する・・・など、筋トレ効率をアップする有酸素運動の取り入れ方については、以下の記事を参考にしてみて下さい。
毎日筋トレのポイント❹ 数日スキップしても挫折しないで!
毎日筋トレをする!と決めても、仕事の都合や体調不良で実現できないこともあります。
だからといってすべてをあきらめてゼロにするのではなく、出来なかったトレーニングを別の日にすこしずつ付け加えたり、
一度に複数の筋肉を動員できるようなトレーニングを活用するようにしましょう。
例えば下半身の大きな筋肉に働きかけるスクワット
上半身を総合的に鍛える懸垂など
多くの筋肉を踏襲できるトレーニングを活用して帳尻を合わせましょう。
週1回の筋トレをする場合のポイント
週1回しか筋トレできないのでは意味がない、と言う人もいますがそんなことはありません。週1回でも、ゼロ回よりは良いことは明白。ただし週2~3回かそれ以上の頻度に比べると効果が出づらいのは確かなので、自重トレーニングよりは、ジムでマシンを使った負荷の高い筋トレを行うことをお勧めします。
週1回の筋トレでは痩せない…という経験がある人は、パーソナル・トレーナーによる効率的なトレーニングをすることで成功体験を得られる可能性が高くなるでしょう。
週1回しかトレーニングできない、という人は以下の記事も参考にしてみてください。
筋トレに最適の時間帯

忙しい日々の中、どの時間帯に筋トレを行えばいいのか、疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。社会人の多くが筋トレを行う朝と夜について、それぞれのメリット・デメリットを解説します。
出勤時間が早くて夜しか時間がとれない会社員なら夜に筋トレを。逆に出勤時間が遅く、夜は接待が多い経営者なら朝がおすすめ。朝と夜が忙しい主婦なら日中。といったように、自分の生活リズムにあった時間帯に筋トレをすることで、習慣化や継続が可能になります。
朝と夜、それぞれの筋トレメリット・デメリットや、リスク回避法については以下の記事を参考にしてください。
筋トレの負荷強度と回数の決め方
筋トレの負荷と回数は筋トレを行う目的によります。筋トレの負荷を表すのがRM(レペティション・マキシマム)。1回しか上げられない重量が1RM、10回上げられる限界の重量が10RMです。
また、筋トレを行う主な目的は以下の3つに分けられ、目的によって重量と回数を変えます。
- 瞬発力・パワー向上
- 筋力UP・筋肥大
- 筋持久力向上
詳しくは、筋トレに最適な負荷と回数を紹介する以下の記事を参考にしてみてください。
毎日の筋トレ 部位別メニュー

筋トレ初心者が自宅で筋トレを行う場合、大きな筋肉から鍛えることで、代謝UPなど、カラダを変える効果が出やすくなります。
そのため大きな筋肉を鍛えるためのパターンA、パターンB、体幹、この3つに分けて、1日3種目×3セットをおすすめします。
- 月:腿・背中・胸(A)
- 火:休養
- 水:休養
- 木:おしり・肩・腕(B)
- 金:休養
- 土:体幹・内転筋・ハムストリング・ふくらはぎ
- 日:休養
パターンA,パターンB、体幹それぞれの筋トレメニューを以下で紹介します。
また、筋トレを底上げするストレッチや、正しい筋トレに有効な神経系トレーニングについても解説します。
週2~3回よりもっと多い頻度で鍛えたい、より筋トレ部位を細分化したい、という方は、レベル別の1週間筋トレメニューを紹介している以下の記事を参照してください。
パターンA:腿・背中・胸におすすめメニュー
腿(もも)・背中・胸の筋トレにおすすめなメニューは主に以下の3つです。
- スクワット(ワイドスクワット)
- 腕立て伏せ
- ベントオーバーローイング
下半身を効率的に鍛える「スクワット」
スクワットは大腿四頭筋をメインに鍛えられる種目です。
- チューブを踏むかダンベルを持つ。体幹を真っすぐにして、脚を肩幅より広く開く。
- 腰をゆっくり下ろす。膝はつま先の方向へ曲げる。膝がつま先より前に出ないように。
- 地面と太ももが平行になるくらいで止めて、上げる。
- 10回ほど行う。
初心者には、大腿四頭筋を集中的に鍛えることが出来るスクワットがおすすめですが、慣れてきたら、一般的なスクワットからつま先を45度外側に開き、ワイドスクワットを行うと、大殿筋、ハムストリングス、内転筋にも効かせることが出来ます。
マシンがあればぜひやりたい「レッグプレス」
レッグプレスはジムのマシンを使用したトレーニング。
マシンに座った状態でフットプレートを足裏で押し上げるトレーニング。スクワットを上下逆さまで行うイメージです。
マシンでお尻が固定されるのでブレづらくいため、通常のスクワットを複数回行うよりも、スクワット→レッグプレスと変化を加えることでより一層下半身の筋肉を追い込むことが可能になります。
- レッグプレスマシンの座面にお尻を突き出すようにしっかり座り込む。
- フットプレートに足首を90度の状態で置く。
- 膝が90度になるまで重量を下ろしていき、スタートポジションまで押し上げる。
骨盤を立たせることを意識する。
腕立て伏せ
腕立て伏せは大胸筋をメインに、三角筋前部、上腕三頭筋を鍛えられる種目。
男らしい胸板やバストアップに有効です。
- 肩幅より少し開いて脇の横あたりに手をついて、うつぶせになる。
- 腰を上げて、頭からかかとまで真っすぐにキープ。
- 肩甲骨を内側に寄せて、胸を張ったポジションをキープ。
- 胸が床につくぎりぎりのところまで、ゆっくりカラダを下ろす。
- 胸を張ったまま持ち上げて、4へ。
- 10回ほど行う。
ベントオーバーローイング
ベントオーバーローイングは広背筋をメインに、僧帽筋、三角筋後部、上腕二頭筋を鍛える種目。逆三角形の背中作りに有効です。
- チューブを踏むかダンベルを持って、足を肩幅に開いて立つ。
- 腰を少し後ろに引いて、腰を真っすぐのまま体幹を前に倒す。
- 胸を張って体幹が真っすぐな姿勢をキープ。
- 肘を後ろに引くように、腰に向かって上げる。
- ゆっくり戻す。
- 10回ほど行う。
パターンB:お尻・肩・腕におすすめメニュー
下半身の筋トレにおすすめなメニューは主に以下の3つです。
- ランジ(サイドランジ)
- デッドリフト
- アップライトロウ
ランジ
サイドランジは大殿筋をメインに中殿筋が鍛えられる種目。
お尻の横にある中殿筋を鍛えられるのでヒップアップに有効です。
- 肩幅に開いて立つ。(負荷が足りない場合はダンベルを持つ)
- 前に踏み出す。このとき体幹は前傾するが、曲がらないように気をつける。
- 太ももが地面と平行のところで止まり、蹴って元の場所に戻る。
- 左右それぞれ10回ほど行う。
初心者には、大殿筋を集中的に鍛えることが出来るランジがおすすめですが、慣れてきたら、サイドランジにすることで、大腿四頭筋、大殿筋、中殿筋、ハムストリングスを総合的に鍛えられます。

デッドリフト
デッドリフトも、大殿筋を鍛えられる種目です。
- チューブを踏むかダンベルを持って立つ。つま先を段差に乗せるとなおよい。
- 膝を動かさずかかとをできるだけ上げる。
- ゆっくり下ろす。かかとが地面についた瞬間に2へ。
- 20回ほど行う。
アップライトロウ
アップライトロウは三角筋中部、僧帽筋上部が鍛えられるメニューです。
- チューブを踏むか、ダンベルを肩幅くらいに持って立つ。
- 肘から上げるイメージで上げる。
- 首の高さくらいまで挙げたら、ゆっくり戻す。
- 10回ほど行う。
ふくらはぎをすっきりさせる「カーフレイズ」
ふくらはぎの筋肉は小ぶりなため、基礎代謝アップには直結しづらいですが
メリハリのある美脚をつくるだけでなく、むくみや疲れ、冷えを改善するなどの生活の質にも直結するので、毎日筋トレをする時間があるのでればしっかりアプローチしたい部位です。
足を腰幅に開いて立ちます。
ゆっくりとかかとを床から離して上げましょう。
勢いをつけず、ゆっくりと床にかかとを下ろす。
1セットを20~30回として3~5セットを目安に行います。
ふくらはぎの筋トレメニューは以下の記事でも多く紹介しています。
体幹おすすめメニュー
体幹のおすすめなメニューは主に以下の3つです。
- クランチ
- バックエクステンション
- ツイストレッグレイズ
クランチ
クランチは腹直筋を鍛える種目。お腹周りを引き締めて、シックスパックを作るのに有効です。
- 仰向けに寝て膝を曲げる。
- 腕は胸の前で組む。(負荷を上げたい人は頭の後ろ)
- へそをのぞきこむように、ゆっくり背中を丸める。(腰は浮かせない)
- ゆっくり戻し、頭が床につく前に3へ。
- 10回ほど繰り返す。
バックエクステンション
バックエクステンションは脊柱起立筋を鍛える種目。しなやかな背中作りに有効です。
- 仰向けに寝て、手を頭の後ろで組む。
- 全身を反らせて、頭と足を上げる。このとき膝を曲げないように。腰だけが床についている状態。
- ゆっくり戻し、頭が床につく前に2へ。
- 20回ほど繰り返す。
ツイストレッグレイズ
レッグレイズに慣れたら、ツイストレッグレイズを追加することで、腹斜筋を鍛え、脇腹引き締め、くびれ作りに有効です。
- 仰向けに寝て腕をカラダの横に伸ばす。
- 膝を伸ばしたまま腰と90度になるまで足を上げる。
- 左右交互に足を伸ばしたまま振る。足が地面につく前に反対に振ること。(足を伸ばせない場合は軽く曲げてもいい)
- 20回ほど繰り返す。
ハムストリングとふくらはぎの筋トレについては、以下の記事を参照してください。
筋トレを底上げする「ストレッチ」
正しいフォームでトレーニングすることが筋トレの効果を出すための基本。
カラダが堅い、関節可動域が狭いといった不具合があると、正しいフォームでトレーニングすることが出来ず、伸び悩みの原因になることがあります。
正しいトレーニングができるよう、トレーニング前や、日常的なストレッチで、肩甲骨周りや股関節まわり、腿裏などの柔軟性を養う動作を取り入れましょう。
筋トレを底上げする「神経系トレーニング」

神経系トレーニングはスポーツのパフォーマンスアップに効果的だと思われていますが、パフォーマンスアップだけでなく、筋トレの効率も底上げします。
その理由は、神経系トレーニングで「意識できる筋肉」「使える筋肉」が増えると、複数の筋肉を連携させて筋トレできるため、筋トレの効果が向上します。
毎日筋トレのメニューに神経系トレーニングを加えることでいつもと違う刺激と効果をブーストすることができます。
筋トレに必要な食事と回復

筋トレの効率を上げるためには
- 正しいトレーニング
- 正しい休養と回復
- 正しい食事
が必要です
そのために毎日筋トレの時間以外で気を付けるポイントを伝えます。
正しい食事
カラダを絞る人は「食べない」という選択肢をすることがありますが、ちょっと待って!
食べない、のではなく、必要な物だけ食べる という発想の転換が必要です。栄養が足りないと、筋肉を分解してエネルギーを作り出してしまう(筋肉が減ってしまう)という悪循環に陥ってしまいます。
特に、タンパク質の摂取は必要不可欠。
筋トレをしない人でも
- 成人男性で最低65g/日
- 成人女性で最低50g/日
のタンパク質摂取が必要です(*2)。
筋トレをしている人は体重1kgあたり1日1.5~2.4gのタンパク質摂取を心掛けましょう。
高タンパク質・低脂肪・低糖質の栄養素はもちろんのこと、ビタミンやミネラルといった代謝にまつわる栄養素をしっかりと摂ることで筋トレ効果をアップすることができます。
食事からだけではとることが難しい栄養素はサプリメントを有効活用しましょう。特に、痩せにくいと言われる40代以降の筋トレやダイエットにはサプリメントを味方につけることで挫折を防ぐことができるのではないでしょうか?
正しい休養と回復
- トレーニング後のストレッチ
- マッサージ
- 入浴
- よい睡眠
これらが傷ついた筋肉の回復力を高めます。筋肉を追い込むだけでなく、しっかりとケアして「回復させる」ことを忘れずに。
【まとめ】自分に合った筋トレ頻度でなりたいカラダを手に入れよう!

部位を分ければ、毎日筋トレを行っても大丈夫です。毎日コツコツと筋トレを行うことで習慣化が早くなる、1つの部位への負荷を上げられるなどのメリットがありますが、現実的には週2~3回の筋トレで下半身と上半身の大きな筋肉を効率的に鍛えるのがベストです。
残りの週4~5日は正しい栄養と回復を心掛けながら、可能であればストレッチやウォーキングなどの軽い運動を追加しましょう。
週1回しかトレーニングできない、という人も、だからと言ってあきらめず、週1トレーニング最適なメニューと長いスパンでのカラダづくりを継続することで、よりよい人生への大きな投資になるでしょう。
時間帯はいつ行っても構いませんので、ライフスタイルに合った続けやすいスケジュールで行ってください。
しかし、筋トレの負荷や頻度などは人それぞれ最適なものがあります。
ただ闇雲にトレーニングをしていても効率が悪いため、効率を上げるには目的ごとのフィットネスライフを提案してもらえるパーソナルトレーニングがおすすめです。プロのトレーナーに最適なスケジュールやメニューを作成してもらうことで毎日の筋トレでもオーバーワークや怪我を避けることができ、週2~3回ないしは週1回しかトレーニングできない、といった場合でも効果を出しやすく挫折しづらいものです。
パーソナルトレーニングについて詳しく知りたい、パーソナルトレーニングは高額でもったいないのではないか?と言った疑問を持っている人は以下の記事も参考にしてみてください。
参考文献
*1 WHOが示す「身体活動・座位行動ガイドライン」
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337001/9789240014886-jpn.pdf?sequence=151&isAllowed=y
*2 日本人の食事摂取基準(2020年版)たんぱく質
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586557.pdf